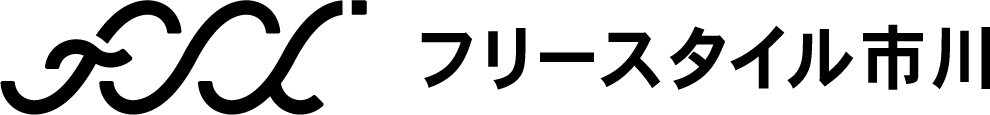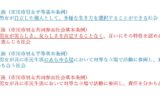1.はじめに:報道は他人事?自分ごと?
近年、マスメディアを通じて、特定の集団に対する排他的な言動や、市民の間に分断を招くかのようなメッセージを発信する政治家が、各地で報じられることがあります。そうした報道に触れる時、胸がざわつくような気がするかもしれません。しかし、どこか遠い場所での出来事のように、他人事のように思う人も少なくないとも思います。
とはいえ、ここ市川市でも、多様な人々を尊重する社会のあり方が問われる場面がないとは限りません。
しかし、市川市は、そうした時代だからこそ、すべての市民が安心して、そして自分らしく暮らせるまちを目指す、明確な羅針盤を持っています。それが「市川市多様性を尊重する社会を推進するための指針」です。
市川市多様性を尊重する社会を推進するための指針
https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/gen05/file/0000457370.pdf
2.市川市が掲げる「多様性を尊重する社会」の指針とは
市川市が令和元年(西暦2019年)6月1日から施行しているこの指針は、私たちの市川市がどのような社会を目指すのかを定めたもので、とても大切な文書です。本当に大切なことがかかれているので、是非、読んでみてほしいのですが(1,700字ちょっとの長さで、わりと平易な語で書かれています)、本稿では、この指針について簡単に説明したいと思います。
指針の「はじめに」には、
「性別、性自認、性的指向、国籍、民族、年齢、障がいの有無等、様々な社会的属性にかかわらず、互いの多様性を認め合い、すべての人が自分らしく暮らせる地域社会を築くことが、いつの時代にも共通する変わらない市民の願いです」
と明記されています。その目的は、
「多様性を尊重する社会を形成し、もってすべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与すること」
にあります。
この指針が掲げる「多様性」。最近、よく聴く、見る言葉ですよね。
「多様性」は、
「性別、性自認(自己の性別についての認識)、性的指向(どの性別を恋愛の対象にするか)、国籍、民族、年齢、障がいの有無等について、人々の持つ個性がそれぞれに異なっていること」
を指します。
3.市が/市民が/事業者が共有する「基本理念」
指針には、多様性を尊重する社会を推進するための三つの基本理念が定められています(文字色は私が強調のために施したものです)。
- すべての人が多様性を認め合い、個人が尊重され、自分らしく生きることができること。
- すべての人が自らの意思に基づき、多様な生き方を選択し、能力を発揮することができること。
- すべての人が社会のあらゆる分野の活動に参画し、責任を分かち合い、協力し合うことができること。
これらは、市川市で暮らす私たち一人ひとりが、互いを大切にし、自分らしい生き方を実現するための土台(ベース)となる考え方です。そして、市川市では、市、市民、および事業者の三者が、一体となって協力することで、これら三つの基本理念の実現に向けて推進していくことを約束しています。
4.多様性社会推進のための具体的な施策と守りたいもの
指針では、上述の三つの基本理念に基づいて、市川市が取り組むべき「多様性社会推進施策」として、いくつかの具体的な方針が示されています。特に注目すべきは、以下のような点です(文字色は強調のために施したものです。私が)。
- 多様な性に対する理解の促進
- 性的マイノリティであることに起因する日常生活の支障を取り除くための支援
- 外国人等への情報の多言語化等、外国人等が安心して安全に暮らせるための支援
- 外国人等との交流の促進
- 外国人等に対する偏見又は差別の解消
- その他、互いの人権を尊重し多様性を認め合う地域社会づくりの推進
これらの施策は、市川市が特定の属性の人々だけでなく、すべての市民が尊重される社会を目指している明確な証拠です。
「●●(特定の属性を持つ人々)ファースト」というスローガンは、「●●優先」や「●●第一」だと解釈できます。
ということは、「●●ではない人々がファーストではない」、つまり、「●●以外の人々は後回しにされる」「●●以外の人々は第二、第三である」と、そうは言っていないにしても、そのように捉えられます。
市川市は、この指針で、特定の属性の人々だけでなく、すべての市民が尊重される社会を目指すと明言していることを覚えておきましょう!
政治スローガンとして使われる、「●●ファースト」は、政策資源や社会的評価を、限られた人に集中させるメッセージとして機能してしまい、「では他の人は?」という問いが常につきまといます(そのため、公共的な文脈で誰を大切にするかを強調するなら、「誰一人取り残さない」「みんなが安心して暮らせる」など、序列を感じさせない言い方が好まれるのですね)。
さて、市民の代表(あるいは代理人とも言えますね)である市議会議員、そして市職員には、これらの基本理念を踏まえ、多様性社会推進施策を実施するために必要な措置を講じることが期待されます。そのような役割を担っていただきたい、ということです。
私たち市民にも、指針の理解促進に努め(そもそも、この指針が存在することを知り、内容を理解しようとしなくてはなりませんね)、地域社会のあらゆる分野でその推進に貢献することが求められています。
5.おわりに:市川市のこの大切な指針の存在を心に留めましょう
社会の分断を招くような言動が取り沙汰される時代だからこそ、市川市が公式に掲げる「多様性を尊重する社会」という指針の価値は、より一層高まります。
この指針は、特定の誰かを排除するのではなく、すべての人が地域の一員として尊重され、安心して暮らせるまちを守り、次世代へとつないでいくための、私たち共通の財産だと言えましょう。
私たちは、この大切な指針の存在を心に留め(つまり、ちゃんと(内容を覚えておこうというと難しいので、まずは、この指針があるんだ、ということを記憶しておきましょう!)、生活において、お互いの多様性を認め合う心を育んでいく必要があります。
そして、もし、私たちの目指す社会の姿と異なる言動が示された時には、この指針に立ち返り、私たちが市川市で本当に大切にしたい価値について、共に考え、対話していくことが重要です。
* * * * *
誰かが何か発言した時、それを聴いた瞬間、「あ!今の発言って無意識かもしれないけれど、差別的かも」と思うことがあるかもしれません。それを見て見ぬふり、聞いて聞かぬふりをして、流すこともできましょう。そうすることで目の前で繰り広げられている楽しく愉快な会話は、滞りなく流れていきます。なめらかに。
そうです。サッカーの審判が目の前で危険なプレーを見たけれども、ファールのジャッジをすぐには下さずに(流して)試合を続行させるかのように、です。
けれども、それは、差別の芽を摘むことにつながらず、あなたの目は差別を見逃す目になっているということでもありますよね。
でも、きっと、自分が「そう感じた」ということは(その場にそれなりに多くの人がいる場合)、他にもきっと「そう感じた」人はいるはずです。「そう感じた」なら、「そう感じた」だけど、と言ってしまってよいと私は思っています。そこから、対話が生まれる可能性があります。
参考:関連記事~色々取り揃えています
多様性について考えながら書いた記事が、何本もあります。色々な種類の記事を取り揃えていますよ。是非、読んでみてください。
蛇足な補足
――多様性を尊重することは、人権と尊厳を守る基盤です。
――人はそれぞれ出自や文化、能力、価値観が異なり、その違いこそ社会を豊かにします。
――誰かの違いを受け入れず排除すれば、平等に生きる権利や自分らしさを保つ尊厳は容易に損なわれます。
――互いを理解し認め合う姿勢は、法制度だけでは保障しきれない日常の人権を支えます。
――多様性を大切にする社会は、すべての人が恐れず自己を表現し、共に成長できる社会です。
――人権と尊厳は多様性尊重の実践の中でこそ息づきます。
先ほど、対話に触れました。言及しました。まちづくりにおける対話には、次のような効果があると思います。
- 理解と共感の土台づくり:互いの背景や価値観を知ることで、偏見や思い込みをほぐし、相手の尊厳を認めやすくなります。
- 合意形成と課題解決:地域の課題を一方的に決めるのではなく、多様な声を聞くことで公平性や納得感が高まります。
- 孤立の防止:マイノリティの人が意見を表明し、支え合える場が増えることは権利保障にもつながります。
と書きましたが、公平な情報提供、参加しやすい環境づくりというのも求められますし、対話の質を高めるファシリテーションのスキルや教育による支援も、成熟したまちづくりには欠かせないと思います。
さらに言えば、対話さえしていればOKというわけではなく、対話に加えて、法や制度による人権保障と差別の禁止があってこそ、私たちが安心して生活できるような環境に近づくのだとも思います。
最後に改めて、すべての市民が安心して自分らしく暮らせるまちを目指す、明確な羅針盤とも言える、「市川市多様性を尊重する社会を推進するための指針」のリンクを貼っておきます。
市川市多様性を尊重する社会を推進するための指針
https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/gen05/file/0000457370.pdf
執筆・公開情報
執筆日:2025年9月17日
公開日:2025年9月17日
執筆者:ノスタルジー鈴木(特定非営利活動法人フリースタイル市川)